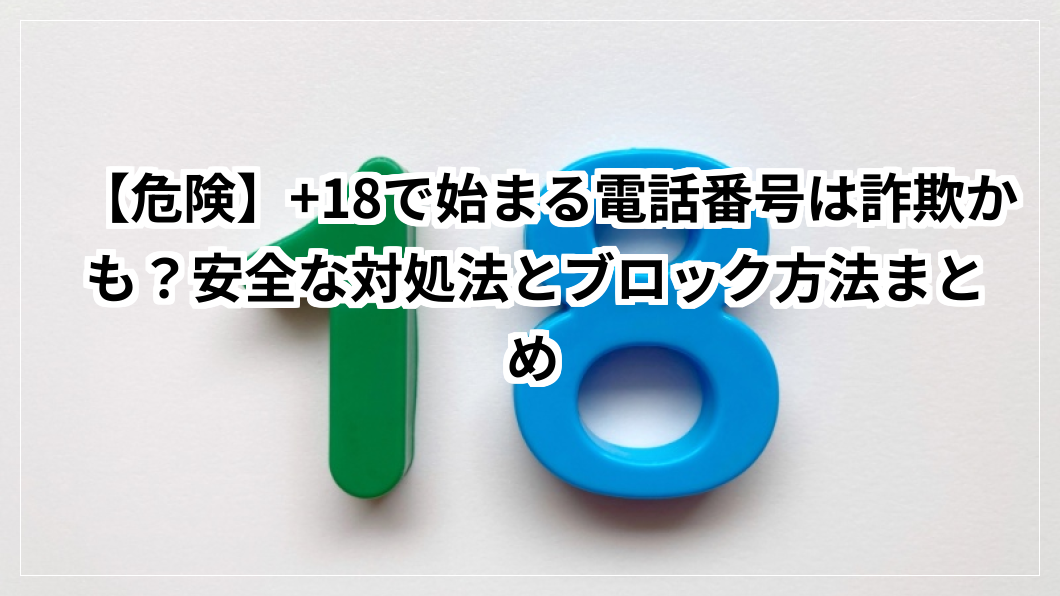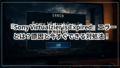最近「+18で始まる電話番号」からの着信が増えているのをご存じですか。
一見すると海外からの普通の電話のように見えますが、実は詐欺目的で悪用されるケースが急増しています。
本記事では、+18番号の正体や実際に起きている詐欺の手口、そしてiPhone・Android別の着信拒否設定までをわかりやすく解説します。
知らない番号に出る前に読むだけで、自分や家族を守る行動が取れるようになります。
+18で始まる電話番号とは?意味と国際番号の仕組み
ここでは「+18で始まる電話番号」が実際にどんな番号なのか、その背景や仕組みを分かりやすく解説します。
一見すると単なる国際電話のように見えますが、実は詐欺電話の温床にもなっているため注意が必要です。
+18の番号はどの国からの発信なのか
「+1」は北米(アメリカ・カナダ)の国番号です。
つまり「+18」で始まる番号は、アメリカ国内の一部地域から発信されているように見える構成になっています。
たとえば「+1812」ならインディアナ州、「+1808」ならハワイ州といった具合に地域ごとに割り当てられています。
しかし実際には、これらの番号を装って他国から発信することも技術的に可能です。
そのため「+18=アメリカからの電話」とは限りません。
| 番号の例 | 表示される地域 | 実際の発信元の可能性 |
|---|---|---|
| +1812 | アメリカ・インディアナ州 | 他国からの偽装発信の可能性あり |
| +1808 | アメリカ・ハワイ州 | VoIP経由で海外から発信されるケースあり |
| +1876 | ジャマイカ | 詐欺目的の国際電話が多発 |
なぜ日本の電話に「+18」で表示されるのか
スマートフォンで「+18」から始まる番号を見ると、国際電話であることを示す「+」記号が先頭に付きます。
この「+」は「国際電話発信の識別番号」で、端末が自動的に付け加えるものです。
そのため、相手が実際にどの国からかけているのかは、番号だけでは判断できません。
番号だけで判断せず、慎重に相手を見極めることが重要です。
国際電話と詐欺電話を見分けるポイント
国際電話か詐欺電話かを見分けるには、次のようなポイントに注目しましょう。
| チェック項目 | 注意点 |
|---|---|
| 相手が名乗らない | 詐欺の可能性が高い |
| 不自然な日本語 | 自動音声詐欺の疑いあり |
| 急な請求・トラブルを伝える | 詐欺の典型的手口 |
| 録音メッセージが流れる | 国際詐欺電話に多い形式 |
これらに当てはまる場合は、電話に出ず、後で番号を調べてから対応するのが安全です。
+18で始まる電話番号を使った詐欺の実態
この章では、実際に報告されている「+18番号」を悪用した詐欺の手口や被害事例を紹介します。
詐欺師たちは、番号を偽装し、あたかも信頼できる国際電話であるかのように装って人を騙します。
よくある手口(架空請求・個人情報詐取など)
最も多いのは「未払い請求」や「アカウント停止」を装う架空請求です。
詐欺師は警察や銀行、宅配業者などの名前を語り、信頼を得ようとします。
また、電話口で個人情報(名前・生年月日・住所など)を聞き出し、後から別の詐欺に利用されるケースもあります。
相手が名乗ったとしても、その情報を鵜呑みにしないことが大切です。
| 詐欺の種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 架空請求詐欺 | 「料金未払いです」と偽り金銭を要求 | 金銭のだまし取り |
| 個人情報詐取 | 「本人確認」と称して住所や口座番号を質問 | 個人情報の不正利用 |
| リダイアル詐欺 | 折り返し電話を誘導して高額料金を発生させる | 通信費の不正請求 |
実際に報告されている被害事例
たとえば、東京都内の主婦・田中美和さん(仮名)は「+1876」からの着信に出たところ、
相手から「未払いの光熱費があります」と告げられました。
慌てて対応してしまい、個人情報を伝えてしまった結果、数日後に不審な請求が届いたといいます。
このように、詐欺師は心理的な焦りを利用して被害者を追い込むのです。
なぜこの番号が詐欺に悪用されやすいのか
理由の一つは、発信元を簡単に偽装できる技術(VoIP)の普及です。
詐欺師はインターネット電話を使って、どの国の番号にもなりすますことができます。
さらに、国際番号というだけで「本物らしく見える」ことも悪用されています。
「+18」番号は、信頼性を装うためのトリックとして利用されやすいのです。
+18で始まる電話番号がかかってきたときの正しい対応
「+18で始まる番号から電話が来たけど、どうすればいいの?」と不安になる人も多いですよね。
この章では、そんなときに慌てず、安全に対応するための具体的な方法を解説します。
電話に出てはいけない理由
まず最も重要なのは、知らない「+18」番号には出ないことです。
詐欺電話の多くは、最初に相手の反応を確認する目的で発信されています。
一度出てしまうと「この番号は有効だ」と判断され、他の詐欺業者に共有されるリスクもあります。
「見知らぬ国際番号には出ない」ことが最も効果的な防御策です。
| 行動 | 結果 |
|---|---|
| 出てしまう | 詐欺リストに登録されるリスクあり |
| 出ずに無視 | 安全に無反応で終えられる |
| 折り返す | 高額な通話料金や情報漏えいの危険 |
もし出てしまった場合の安全な対処法
万が一出てしまった場合も、落ち着いて行動することが大切です。
相手が「未払い」「本人確認」などを口にしても、慌てて答えないでください。
「確認してから折り返します」と伝えて通話を切るのが安全です。
会話の内容は可能であれば録音し、後で警察や消費生活センターに相談しましょう。
また、通話後にはその番号をブロック登録するのも忘れずに。
| 状況 | 適切な対応 |
|---|---|
| 個人情報を聞かれる | 「答えられません」と断る |
| 金銭を要求される | 即座に通話を終了 |
| 内容を録音できる | 証拠として保存 |
相手の正体を確認するためのチェックリスト
怪しい電話を受けたときは、以下のチェック項目で判断してみましょう。
| チェック項目 | 判断の目安 |
|---|---|
| 相手の名前と所属先を名乗ったか | 名乗らない場合は詐欺の可能性大 |
| 日本語が不自然でないか | 自動翻訳音声なら要注意 |
| 折り返し連絡先を伝えたか | 伝えない場合は信用できない |
| 公式サイトや連絡先が存在するか | Googleなどで確認可能 |
少しでも不審に感じたら、その場で通話を終える勇気を持ちましょう。
スマホでできる+18番号の着信拒否設定方法(機種別)
不審な番号に何度もかけられるのはストレスですよね。
ここでは、スマートフォンの機種ごとにできる「+18番号の着信拒否方法」を分かりやすく紹介します。
iPhone(iOS)のブロック設定手順
iPhoneでは標準機能で特定番号のブロックが可能です。
以下の手順で簡単に設定できます。
| 手順 | 操作内容 |
|---|---|
| 1 | 電話アプリを開き、「履歴」タブをタップ |
| 2 | 「+18~」で始まる番号の横にある「i」アイコンをタップ |
| 3 | 下にスクロールして「この発信者を着信拒否」を選択 |
| 4 | 確認画面で「着信拒否」をタップ |
なお、iPhoneでは「番号の一部(例:+18*)」を条件にブロックすることはできません。
個別の番号ごとに拒否登録する必要があります。
Androidスマホのブロック設定手順
Androidの場合は、メーカーやOSバージョンによって操作が多少異なります。
基本的には次のように設定します。
| 手順 | 操作内容 |
|---|---|
| 1 | 電話アプリを開く |
| 2 | 右上のメニュー(︙)から「設定」を開く |
| 3 | 「ブロック設定」または「迷惑電話の設定」を選択 |
| 4 | 「番号を追加」で「+18~」を入力して登録 |
一部機種では「+18*」のようにワイルドカードを使って複数番号をまとめてブロックできます。
ただし機種によっては完全一致のみ対応している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
ドコモ・au・ソフトバンクなどキャリア別の対策
主要キャリアでも、迷惑電話対策サービスを提供しています。
| キャリア | サービス名 | 特徴 |
|---|---|---|
| ドコモ | あんしんセキュリティ | 自動で迷惑電話番号を検知・ブロック |
| au | 迷惑メッセージ・電話ブロック | AIが不審な発信元を自動判別 |
| ソフトバンク | 迷惑電話ブロック(有料) | 最新の迷惑番号データベースを使用 |
これらのサービスを活用すれば、「+18」から始まる不審な番号を自動的にシャットアウトできます。
スマホだけでなく、通信会社のサービスも併用するのが最も安全です。
迷惑電話と詐欺電話の見分け方
「この電話、ただのセールス?それとも詐欺?」と迷った経験はありませんか。
ここでは、迷惑電話と詐欺電話の違いを整理し、どのように見抜けばよいのかを具体的に解説します。
迷惑電話の特徴と対応策
迷惑電話は、営業目的や勧誘など、法律違反ではないもののしつこく何度もかけてくる電話を指します。
代表的な例としては、リフォームの勧誘、保険のセールス、無言電話などがあります。
詐欺ではなくても、日常的なストレスになるため、ブロック設定を活用して対応することが大切です。
| 迷惑電話のタイプ | 特徴 | 対処法 |
|---|---|---|
| セールス電話 | 商品・サービスの勧誘目的 | 着信拒否リストに登録 |
| 無言電話 | 相手が沈黙して反応を伺う | 反応せず通話を切る |
| アンケート電話 | 情報収集を装うケースあり | 個人情報を答えない |
また、電話に出た際に「この電話は録音されています」と一言伝えるだけでも、迷惑業者は警戒して再度かけてこなくなる傾向があります。
詐欺電話の兆候を見抜く3つのサイン
詐欺電話には、いくつかの共通する特徴があります。
以下の3つのサインがあれば、すぐに詐欺を疑いましょう。
| サイン | 内容 | 危険度 |
|---|---|---|
| 1. 緊急性を強調する | 「今すぐ対応しないと」「支払い期限が今日中」など | 非常に高い |
| 2. 金銭や個人情報を要求 | 振込先や口座番号を伝えるよう促す | 高い |
| 3. 相手の素性が不明確 | 会社名・担当名を曖昧にする | 中程度 |
特に、金銭を要求する電話は即座に切るのが鉄則です。
相手が「警察」「金融機関」などを名乗っても信用せず、公式窓口に自分で確認しましょう。
被害を防ぐために日常的にできる予防策
詐欺電話の被害を防ぐには、日ごろからの準備が何よりも大切です。
次のような習慣を身につけておくと安心です。
- 知らない番号は出ない
- 通話は録音機能をオンにする
- 着信拒否機能を常に活用する
- 家族間で詐欺事例を共有する
- 迷惑電話対策アプリを導入する
日常的な予防こそ、詐欺電話に強くなる一番の方法です。
警察や公的機関への相談・通報の流れ
もし怪しい電話を受けてしまったら、自分で抱え込まずに公的機関へ相談することが重要です。
ここでは、通報・相談の手順と準備しておくべき情報を紹介します。
どこに相談すればよいのか(警察・消費生活センターなど)
主な相談先は以下の通りです。
| 相談先 | 連絡方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 警察相談専用ダイヤル | #9110 | 緊急性のない詐欺・迷惑電話の相談 |
| 消費者ホットライン | 188 | 全国の消費生活センターにつながる |
| サイバー警察窓口 | 各都道府県警の公式サイト | ネットや国際電話に関する被害 |
特に「#9110」は全国共通で利用でき、平日は警察相談員が丁寧に対応してくれます。
通報時に準備しておくべき情報
通報時には、次の情報を整理しておくとスムーズです。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 日時 | 電話がかかってきた日と時間 |
| 相手の番号 | +18で始まる具体的な番号 |
| 会話の内容 | 請求・個人情報要求などの内容 |
| 被害の有無 | 金銭や情報を渡したかどうか |
録音やスクリーンショットなどの証拠も、警察に提出すると非常に有効です。
実際に相談した後の対応の流れ
相談後は、警察やセンターが内容を精査し、必要に応じて被害届の提出や事業者への注意喚起が行われます。
また、悪質な電話番号は各通信事業者と共有され、全国的にブロック対象となることもあります。
早期に通報することで、他の被害者を救うことにもつながります。
まとめ:+18電話番号から身を守るために知っておくべきこと
ここまで「+18で始まる電話番号」に関する危険性と対策を詳しく見てきました。
最後に、この記事の要点を整理し、安全にスマホを使うためのポイントをまとめます。
本記事の要点と安全対策の再確認
まず、+18で始まる電話番号は一見すると海外からの正規の国際電話に見えますが、実際には詐欺や迷惑電話に悪用されるケースが多発しています。
そのため、知らない「+18」番号には出ず、必ず番号を調べてから対応しましょう。
| リスク | 対策方法 |
|---|---|
| 詐欺目的の架空請求 | 出ない・折り返さない |
| 個人情報詐取 | 会話で情報を伝えない |
| 高額通話料金請求 | リダイアルしない |
| しつこい迷惑電話 | 着信拒否・ブロック設定 |
また、iPhone・Androidともに着信拒否機能を設定しておくことで、将来的な被害を防止できます。
キャリアの提供する「迷惑電話ブロック」などのサービスも積極的に活用しましょう。
不審な電話に出ない・情報を渡さない・通報する。この3つが安全を守る基本です。
家族や高齢者にも共有すべき注意点
詐欺電話の多くは、高齢者を狙ってかけられます。
スマートフォンの操作に慣れていない家族がいる場合は、ブロック設定や対処法を一緒に確認しておくことが大切です。
また、実際の詐欺電話の音声例やニュースを家族で共有することで、注意意識を高めることができます。
| 対象 | 推奨する対応 |
|---|---|
| 高齢者 | 家族がブロック設定を代行 |
| 子ども | 知らない番号は出ないと教える |
| 家族全体 | グループLINEなどで注意喚起 |
「知っておく」ことが最強の防御です。
この記事で紹介した内容をぜひ家族や友人にも共有し、みんなで安全なスマホ利用を心がけましょう。